なぜかつての日本人の心は強かったのか?③
「精神のバランス」のもう一つの意味は、「心と精神と身体」の三つで私は人間を捉えているが、その中での「精神の担う領域が小さくなり過ぎて、バランスが崩れている」という事だ。
精神を継承し、整え、鍛える。
この作業に日本人は多くエネルギーを掛けてきた。しかし、現在は精神を強くする事より、心の問題にかかずらい過ぎている。
「精神と身体(習慣)の領域を回復させる事で、内面のバランスが整う」と私は考えている。
「甲子園」の高校野球から、私達は「精神のカタチ」を感じる。
甲子園に出場しなかった者達も、「甲子園という精神」を共有している。「全力を尽くして、キビキビと、力をあわせて戦い抜く」精神の在り方は、一塁への全力疾走を見るだけでも分かる。
だからこそ、大会中に、いや試合中にさえ、成長する。
精神が成長すれば、技も整う。甲子園という場が精神を育てている。そして大会の継続が、精神の継承になっている。
二十年前、五十年前の球児達と、現代の球児達の精神の間に大きな違いはおそらくない。
甲子園という精神が、多くの勢い溢れる教育者達によって絶え間なく継承されてきたのだ。
甲子園を目指して練習に打ち込んだ球児達は、一つの「精神」が自分の中に根付いた事を感じる。
大人になっても、「その精神が心を支えてくれている」のを折にふれて感じるだろう。
精神は、日本古来のものである必要は必ずしもない。野球にせよ輸入品である。仏教や儒教、漢文なども輸入品だ。ゲーテやドストエフスキーやトルストイといった偉大なる精神が日本の青年達の精神を形成してきた。
国粋主義ではバランスが狂う。私が言いたいのは、あくまでバランスだ。森の様に多様で豊かな「精神の森」をつくる事だ。
読書は、精神の森をつくる王道だ。なぜなら精神の多くは、言葉を通じて継承されてきたからだ。「精神を学ぶ読書」をするかしないか、これだけで心の強さは変わってくる。
心という移ろいやすいものをバランスよく鍛えるために、「精神」に目を向け直し、「精神の森」を培う事にエネルギーを注ぎ込む事をこの本で提案したい。
これまでの私の研究を結実させた「精神バランス論」を世に問いたい。
齋藤孝
(明治大学 教授)
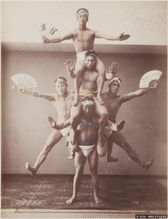
「心」という時は、
自分の中の「我・エゴ・私心」を表している事が多く、
「精神」という時は、
自分を外側から俯瞰し手見ている「真我・ハイヤーセルフ・公の自分」を表す事が多いのだと思う。
日本人であれば、「大和魂・日本精神・日本男児・大和撫子・サムライ」といった言葉を口にした時、自然と自分の内に在る「強い自分・公の自分」を引き出している様に感じます。
だから「なでしこジャパン」とか「サムライブルー」とか言った言葉が受けるんやろうなと思うんですよね。
「サムライ」とか言ったって、ほとんどの日本人の先祖は農民か漁師、木こりでしょうから、本来ならサムライとか全然関係ないでしょうし。
でも、「サムライ」という日本の精神性を象徴する単語を口にした瞬間、民族の歴史や伝統を背負う感覚が無意識に生まれるんやろうと思うんですよね。
今の日本人はこういうのを右翼的と感じる人が多いでしょうけど、アメリカ人なら「フロンティアスピリット」とかがそういった言葉になると思うし、どんな国や民族にでも、その内なる誇りを感じさせる、蘇らせてくれる言葉というものがあると思う。
齋藤孝さんがおっしゃる様に、人間の弱い心を支えてくれる「民族の文化や伝統、誇り」を理屈抜きに感じさせてくれるのが、精神や身体文化(習慣)なのだと思います。
「家系のシステムや伝統」といったものは、今では悪く言われる事の方が多いけれど、「〇〇家の人間として恥ずかしいマネは出来ない」といた価値感が、個人の弱い心を支えてくれていた部分は凄く大きいと思うんですよね。
勿論、これも生き過ぎると、個人を圧迫し過ぎるからバランスは大切ではあるけど、悪い事ばかりじゃない。
その言葉を聞いた瞬間、思わず「背筋が伸びる」といった精神性を伝えてくれる文化や伝統は、一人では弱い存在である個人を支えてくれる有難い文化やと思うんですよね。

