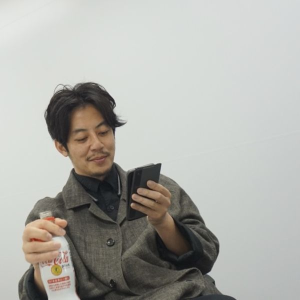「停止」と「静止」の違い
考えさせられるとても良い文章を読んだので、紹介します。
ピアニストの早川菜穂子さんのFacebook記事。僕は音楽の事はよく分からないけど、このりんごの例は凄く分かりやすいですね。
りんごが机に止まっているのも、
重力とそれに相反する力がそこに常に働いているからで、、。
実は止まってはいないのですよね?
周りから解らないとても微細な世界でもありますが、
常に変化しているものが、本当に善い、自然なもの。。
私たちの身体もそうですよね
揺らした方が治ったりするのもその為だと思います。細やかなバランスがとられる。
そのためには、ある周波数も、その隣の周波数も大切で
いつもそれを基本に持っておくと、
「囚われ」を作る噂に流されることは無いと思います
この世界は全てが常に流れていて、ある一定の状態に留まる事はない。
僕は武道で「停止」と「静止」の違うのだ、と教わりましたが、宇宙に存在する一切のものは「停止」する事はないんですよね。一見、止まっている様に見えても、それは「静止」。
人間の欲・エゴだけが、その流れを止めて「停止」させてしまう。
氣・エネルギーが切れた状態が「停止」で「死」に近いもの。
氣が通り、エネルギーに満ちているけれど、周囲の環境とのバランスで一時的に止まっている様に見えるアイドリング状態が「静止」だと思う。
「こだわり」は行き過ぎると、「執着」になり、それはエネルギーが滞った状態で自然の流れを止めた、まさに不自然な状態。
頭デッカチな人、体験が伴わず知識のみが先行しがちな人は、この頭でのみ考えた理論に「執着」してしまう。
自分で宇宙の流れに逆らい、そこに留まろうとしている。この宇宙の大いなる流れを止めてしまう事を「罪」とか「悪」というのだと思うんですよね。
以下に全文を転載しておきます。
一個人の、ただの私の感覚ですが、
よく聞かれるので。。こちらにも
流行っている周波数?
私はむしろ、その流行りの方が多少危険に感じています。
イギリスの昔の歌手のその音を聴かれましたでしょうか?
私は気持ち悪くて聴けませんでした、、
(なのでここにも置きません
)
むしろ、魔的な音が意図的に作られた作品だと思いました。(「目」の印が象徴する通り。。)
(ご本人のメロディーには普通に和声変化があるので(だから実質1和音でもなく。。1和音で作られているというのも音楽理論的な説明上間違いです。。
1和音を無理矢理ずっと下に置いているだけで、メロディーにはちゃんと和声変化があります)、あの様にしたのはプロデューサーさん?)
幸い、楽器でしたら勝手にピッチは変わってゆくので(オケも)、440でも442でも、432でも425でも、本当に微細に変わり合い、そこにずっとstayするなんて事はないです
むしろ、できないものです。空気が、常に楽器を微細に変えるので
だから、奏者は微細に調整するのですね
また、その手の記事で、昔は〇Hzだった、などと書いてあるのも間違いで、
18世紀・19世紀は、各都市ごと、各劇場事に細かくピッチが違いました。
同じ国でも、A415〜425~455Hzくらいの違いが各所であったのです(笑)
その土地、その人々のテンション、気候に合わせて自然にそうなったのもあると思います。(残っているチューニングフォークがそれを示しています)
そして、機械の音で、ずっと同じ周波数を浴びるようなものの方が不自然であり、
それはどんな周波数であれ、
同じ1音を浴び続けると洗脳的になります。
健康な人は、固定された周波数は気持ち悪くなると思います
一部分だけを良くしても、全体バランスをとらなければ効果もないでしょう。
また、昨日に良い音と今日に良い音も違い、、人によっても違い。
○〇Hzが良い、を押し付けるのではなく
その時々に快適になれる響きに自分で気づける、選択できる、
それを自分で微調整できる感性の方が遥かに大切です。
ですので、〇〇が良い、というのはある意味、
囚われになってしまうのですね。。
先に「自分の身体で」感じる事を、”捨てさせて”しまうからです。
感性or理性(人間の力)を捨てさせ、何かに憧れさせ依存させる、、
これはいつもながらの、
魔的なものの性質ですよね。。
この世の真理だと思いますが、自然なものは、
かならず揺れ、動き、伸縮し、同じではなく。
バレリーナさんなど、止まって見えるものも、
実は動き(伸ばし)続けている。。
止まるためには、エネルギーを送り続ける必要があります
りんごが机に止まっているのも、
重力とそれに相反する力がそこに常に働いているからで、、。
実は止まってはいないのですよね?
周りから解らないとても微細な世界でもありますが、
常に変化しているものが、本当に善い、自然なもの。。
私たちの身体もそうですよね
揺らした方が治ったりするのもその為だと思います。細やかなバランスがとられる。
そのためには、ある周波数も、その隣の周波数も大切で
いつもそれを基本に持っておくと、
「囚われ」を作る噂に流されることは無いと思います
良い周波数を浴びたいのなら
心地良く揺れている
波の音を聴く、木々の囁きを聴く、
子供たちの声を聴く、、
機械に頼らなくとも、既に、
この地球に多く与えられていますね
人間が作り出したものは、所詮人間レベル?(笑)
大いなる自然に勝るものはないかと。。
そんな訳で、
歴史的な作曲家さん、芸術家さん達の「先生」は、
いつも最終的に、人間ではなく
「自然」でした。
“人間を師にしてはいけない。”
これは、人間を崇拝する人、
また自分を崇拝してほしい人には、
傲慢で、邪魔な聞こえる言葉かもしれません。
でも、本当に謙虚な人とは、
その様な、人間を師にしない状態だと、
私はいつも思っています。
そうすると、弟子に対して
傲慢になることもないでしょう?
私達は皆で、「偉大な何か」を師とする。
そしてそれは、”自分の”身体の中にも
既に与えられていて。
身体という、自然の神秘。
だから、「偉大な何か」を信頼していると
既にそれらが与えられている人間そのものも、
一人一人、奥底で信頼できるのです
「師」に関する部分は、僕は考えが違うけれど、多分、音楽の世界では「縛り」がきつくてこういう表現をされているんじゃないかな?という気がします。音楽は実際に「音」(レコードやCDといった音源)であったり、「楽譜」というもので、一応「形」になったものが存在するので、そこから学んで一人で独習していく、という形も有効なのかも。
武道とか、「独学」では絶対に無理やし、何よりもケガや故障が付きまとう。勿論、「一人稽古」というものは非常に重要でそれがないと上達しないけれれそ、その最初の段階ではとにかく徹底的に「基本の型通り」に行う事を要求される。
そうやって、師について「守・破・離」という段階を踏んでいく中で、自然に「師から離れていく」時期を迎えていく。
とはいっても、精神的な意味ではずっと師であるし、子供が成長して親離れしていく姿に近いものかな?と思うけれど、でもそこにも「ある一定の場所に留まらない」という意味で「停止しない」「流れていく」という日本的な思想があるのだろうと思います。